子どもが体調を崩したとき、「これって病院に行くべき?」「様子を見て大丈夫?」と迷うこと、ありませんか?
私自身、初めての子どもの発熱でパニックになったひとりです。
医療職として働いていながらも、いざ自分の子となると勝手が違い、
夜になるにつれ熱が上がるわが子を前に、ただただ不安でいっぱいでした。
今回は、そんな私が実際に頼った相談先や、備えておけばよかったことをまとめました。
いざというときに焦らないためにも、この記事が「知っておいてよかった!」と思ってもらえるような情報になればうれしいです。
・#8000(小児救急電話相談)は心強い味方。ただし、つながらないこともある
・つながらないときに備え、書籍やガイド・相談先の一覧を準備しておこう
・診察券・保険証・母子手帳はひとまとめにしておくと安心
・知識も大事だけど、信頼できる家族やママ友に相談するのも◎

出産後初の体調不良で大混乱!#8000につながらない⁉︎
慣らし保育が始まって3日目の夕方、娘が急に嘔吐し、発熱しました。
出産後初めての体調不良。
準備なんて何もしていないし、「看病ってどうやってするんだっけ?」と焦るばかり。
私は普段、医療従事者として働いていますが、いざ自分の子となると、勝手が違うもの。
不安と焦りで頭が真っ白になり、ひとまずかかりつけ医からもらっていた小児救急のガイドを読み返しながら、#8000に電話をかけました。
でも、何度かけてもつながらない。
10回以上かけても音声ガイダンスで切れてしまう。
その間にも娘の熱はどんどん上がり、心配は募る一方でした。
そこで、先輩ママである姉に電話して状況を相談。
「経口補水液があるといいよ」とアドバイスをもらい、急いでドラッグストアへ走りました。
このとき、信頼できる人に頼ることの大切さを実感しました。
ようやく#8000がつながったのは、電話をかけ始めてからしばらく経った後。
オペレーターの方は丁寧に娘の様子を聞き取ってくれて、的確なアドバイスをいただき、
ようやくホッと一息つくことができました。
しかし、解熱剤もなく、高熱の娘が心配で私は一晩中こまめに起きては熱を測ったり、水分をとらせたり。
この経験から、「備えって本当に大事」だと痛感しました。
#8000ってどんなサービス?基本の知識をおさらい
そもそも、#8000って?
そんな方のために、まずは基本情報をまとめました。
#8000とは?
・夜間や休日に子どもの体調不良で迷ったときに相談できる電話サービス
・小児科医や看護師がアドバイスしてくれる
・全国共通の番号(#8000)でつながる
「夜間に発熱」「休日に嘔吐」など、すぐ病院に行くべきか悩んだとき、#8000はとても頼りになるサービスです。
この番号にかけると、地域ごとに設置されている窓口につながり、小児科医や看護師が子どもの症状を聞きながら、対応のアドバイスをしてくれます。
たとえば「朝まで様子を見ていいか」
「今すぐ救急に行った方がいいか」など、
判断に迷うケースでも、的確なサポートを受けることができます。
子どもは急に体調を崩すことが多いので、夜間・休日に相談できる場所があるのは心強いですね。
利用方法と注意点
- 携帯・固定電話のどちらからでも「#8000」でつながる
- 都道府県によって対応時間が異なるので、事前に確認しておくと安心
- 混雑していてつながりにくい場合もある
#8000は携帯電話・固定電話のどちらからでも利用可能です。
ただし、対応している時間帯は自治体によって異なるため、事前にチェックしておくことが大切。
特にインフルエンザや感染症が流行する時期は、電話が集中しやすく、「全然つながらない!」という事態になることも。
実際に私も、体験談でお話ししたように、10回以上かけてやっとつながりました。
つながりにくいときの代替策(書籍・相談先リストなど)もあわせて準備しておくと、焦らず対応できます。
実際に相談したときの流れと印象(体験談)
- 症状や経過を丁寧にヒアリングしてくれる
- 医療機関に行くべきかどうかの判断をしてくれる
- 精神的にも落ち着ける声かけがあり安心できた
娘の発熱で#8000にようやくつながったとき、オペレーターの方がまず丁寧に症状を聞いてくれました。
「いつから発熱しているか」「嘔吐はあったか」「水分は取れているか」など、順を追って確認してくれるので、こちらも落ち着いて話すことができました。
相談の結果、「今すぐ夜間受診は必要ない」「水分補給を意識して、翌朝の診察を」
とのアドバイスを受けその場で大きな安心感につながりました。
また、単に情報を伝えるだけでなく、
「不安だったらまた電話して大丈夫ですよ」と声をかけてもらい、
心まで少し軽くなったのを覚えています。
#8000がつながらないときの相談先3つ
信頼できる家族・ママ友に相談
- 自分の不安を整理するきっかけになる
- 育児経験者ならではのリアルなアドバイスがもらえる
- 判断に迷ったときの“背中を押す存在”にもなる
私が初めて娘の体調不良を経験したとき、一番に電話したのは、先輩ママの姉でした。
「子どもが熱を出したら、まずは水分補給」「経口補水液は常備しとくと安心だよ」など、
経験者だからこその言葉がとても心に響き、冷静さを少し取り戻すことができました
とくに#8000がつながらないような状況では、すぐに判断できずに迷う場面もあります。
そんなとき、育児経験のある人の“リアルな助言”は、医療的な情報以上に心を支えてくれます。
小児救急ガイド・信頼できる書籍
- 相談先が不明なときも「自分で判断できる軸」を持てる
- 夜間などネットで調べにくいときにも対応できる
- 事前に読んでおくことで“焦らない力”が身につく
医師から紹介された小児救急の本や、自治体が配布している「こどもの救急ガイド」は、
いざというときの判断材料になります。
私はあらかじめ大事そうな部分にマーカーをひいておいたので、夜中に慌ててページをめくっても、
すぐ必要な情報にたどり着けて、冷静に判断することができました。
インターネットも便利ですが、信頼性にバラつきがありますし、夜中に目を酷使してスマホを見続けるのも辛いもの。
やはり、紙で手元に「自分で調べられるツール」がある安心感は大きいです。
自治体のサポート窓口(LINE/電話など)
- 自治体によっては独自の相談先がある
- LINEやウェブチャットなど、気軽に使えるものも多い
- あらかじめリスト化・印刷しておくと安心
#8000のような全国共通の窓口に加えて、自治体が用意している地域の相談窓口がある場合もあります。
「この程度で相談していいのかな…?」と迷うようなケースでも、
LINEなど気軽な手段でアクセスできると、
ママのメンタル面にも大きな安心材料になります。
特に夫婦間で情報共有するなら、相談先リストを紙に印刷して冷蔵庫などに貼っておくと、
いざというときに誰でも対応できますよ。
相談前に備えておくと安心な3つのこと
ここからは、いざというときに焦らないための、対策法をお伝えします。
診察グッズをひとまとめに
- 母子手帳・保険証・医療証・診察券などを1か所に
- 夜間や緊急時にもすぐ持ち出せるように
- 夫婦で置き場所を共有しておくとより安心
私は、母子手帳ケースに診察券や保険証、医療証、筆記用具や現金までまとめて入れて、
「これひとつ持てばOK」という状態にしています
体調を崩した子どもを抱えながら探し物をするのは、とても大変。
「持ち出しセット」がまとまっていれば、病院に行くか迷ったときでも、スムーズに動けます。
もちろん、置き場所は夫とも共有。
いざというときに自分が不在でも、家族がすぐ動けるようにしておくことが大切です。
書籍・ガイドを読んでおく
- 体調不良時に読むのではなく、元気なときに一度目を通す
- 重要なページは付箋やマーカーで印をつけておく
- 夫婦で共有することで、判断のズレを防げる
私は、かかりつけ医からすすめられた小児救急の書籍を、時間があるときに読んでいました。
特に「何度も読む必要がありそう」と思った箇所には、マーカーや付箋で目印をつけておくのがポイントです。
一緒に子育てをしているパートナーとも内容を共有しておけば、夜中や休日にどちらが対応する場合でも、判断の基準を揃えることができます。
相談先リストをスマホ or 紙にまとめる
- スマホのメモアプリやGoogle Keepに一覧保存
- 紙で印刷して見やすい場所に貼っておくのも◎
- 夫婦や同居家族で共有しておくといざというとき安心
#8000以外にも、かかりつけ医・夜間救急・地域の健康相談ダイヤルなど、
頼れる相談先は事前に一覧にまとめておくのが安心です。
私はスマホのメモアプリにまとめていますが、万が一スマホが使えないときのために、
紙に印刷して冷蔵庫に貼り、家族にも周知してあります。
不安なときは、何より「すぐに相談できる」ことが心の支えになりますよ。
まとめ:「知らない不安」を「備えた安心」に変えよう
今回は、子どもが体調を崩したときに相談できる先と、備えておくと安心なことについてまとめました。
✔ #8000はとても心強いけれど、つながらないこともある
✔ 書籍やガイド、家族・地域のサポートなど、複数の「相談の窓口」を知っておこう
✔ 診察グッズや相談リストをまとめておけば、いざというとき慌てず対応できる
「焦らず、落ち着いて看病する」ために、日頃からの準備はとても大切です。
初めての発熱に戸惑っているママやパパに、この記事が少しでも役立てばうれしいです。
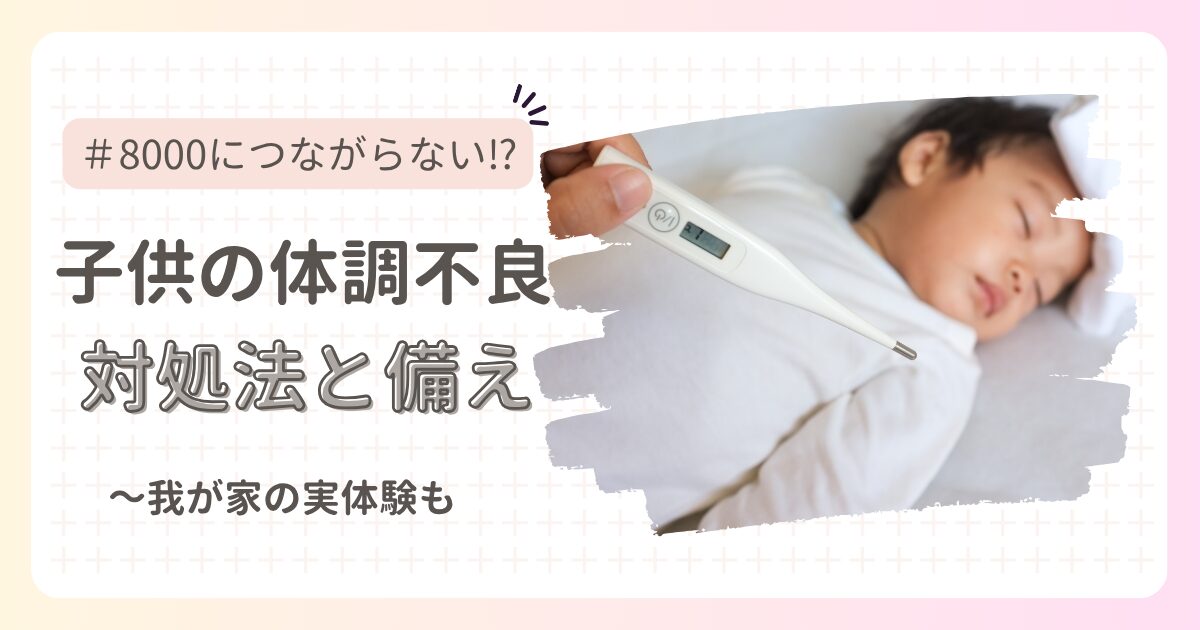





コメント